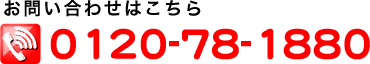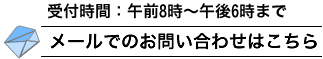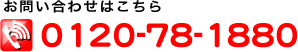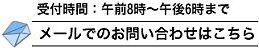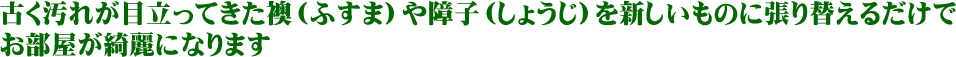
襖(ふすま)と障子(しょうじ)を楽しみましょう
襖(ふすま)は日本古来より部屋と部屋を仕切る「間仕切り」建具として使われました。
しかし、近年では部屋の仕切は壁に変わり、襖(ふすま)の数も減りました。
特に最近の住宅では和室が無い家も多く、襖(ふすま)が全くない家もあります。
襖(ふすま)は、木で組んだ格子状の骨格に和紙の下張りを貼り、その上に襖(ふすま)紙を貼って仕上げます。
壁紙と違い、簡単に貼り替えることができるので、部屋の模様替えやその空間の雰囲気により、貼り替えて楽しむことができます。
最近は印刷技術が進化し、様々な紋様や模様が出てきました。
既製品に物足りない人は無地の紙に絵や書を書き、それを襖紙として使うこともあります。
また、引き手もたくさんの種類があります。
組み合わせ次第で、その部屋のもつ趣に合わせた襖(ふすま)を作り出すことが出来ます。
襖(ふすま)と並んで日本古来の建具として欠かせないものが障子(しょうじ)です。
襖(ふすま)と同じように部屋の間仕切りとして使われますが、その大きな違いは採光にあります。
日中の太陽の光を優しく取り込む、蒼い月明かりを取り込む、といった「侘(わび)・寂(さび)」は障子(しょうじ)の果たす役割が大きいですね。
大事なお客様をお迎えする時、和室の模様替えをしたい時、畳を替えた時などは貼り替えをおすすめします。
また、貼り替えだけではなく、襖や障子の補修の時もお電話いただければ、襖・引き手等の見本を持ってお伺いします。
ぜひ、お問い合わせください。









襖(ふすま)の機能
襖とは、使用する部材の木部は建築端材もしくは間伐材を用い、下貼紙には再生紙あるいは反故紙(貼り替え時に新聞紙やチラシなども使います)を多用し、上貼紙には多く楮や三椏といった栽培植物を原料とする紙を用いるといった極めて「エコ」な物です。
その上、メンテナンスを伴うことにより、何代にも亘って継続使用できます。
今の時代にピッタリな建具です。
また、引手材として多用する銅には極微量作用といい、わずかの量で驚くほどの抗菌作用があるため、衛生上も優れています。
さらには脱臭性、大気汚染等による有害物質の高い吸着性、また高い調湿性を備えた下貼の存在、および上貼紙の持つ血圧降下作用もあります。
「エコ」で「健康的」でかつ「芸術的」。
こんな素晴らしい建具がどんどん日本人の住宅から無くなっているのです。
もう一度、襖の素晴らしさを見直してみませんか?

障子(しょうじ)の特徴
(1)ぬくもりを感じる風合いと目に優しい採光機能
障子(しょうじ)の紙は光の透過率が40%から50%といわれています。
ガラスのような透明なものと壁などの遮断物の中間にあるものと言えるでしょう。
障子(しょうじ)は日当りの暖かさを残しつつ、直射日光を適度に遮り、UVカットにも役立っています。
そして、障子(しょうじ)に差し込んだ光は、各方向に拡散してどの方向から見ても均一に美しく明るく見え、室内全体を同じ明るさで、やさしくつつみこみます。
採光機能こそが障子(しょうじ)紙をインテリア材に選ぶ一番の理由でしょう。

(2)鎮静効果
紙を通して差し込む柔らかな光は、ストレスがたまりがちな現代人の神経を和らげる鎮静効果があります。
障子(しょうじ)紙の5つの効果として、次のような指摘がされています。
- 日光のすべての光と色を室内に伝えるので体が健康になります。
- 室温が外より高まると熱を外へ放出し、その逆の作用もします。
そのため夏は涼しく冬は暖かくなります。 - 湿度に関しても同様に調節します。
- 空気を濾過します。
外気が障子紙を通って室内に入るとき、タール色素や排ガスの微粒子であるニトロン化合物などの発ガン物質を吸着します。 - 強い光をやわらげ、均斉度のある明るさを提供します。
このように、障子紙(しょうじ)は健康にとてもいい影響を及ぼしています。

(3)高いデザイン性
障子(しょうじ)といえば和室=古風というのが一般的なイメージですが、少し見方を変えると、障子(しょうじ)はとても現代的デザインと言えます。
紙の「白」と木の棧の「ベージュ」のシンプルなデザイン。
それに加えて木や紙の自然味あふれる素朴な暖かさ。
自然やシンプルライフを強く求めている現代にぴったりのインテリア素材と言えるのではないでしょうか。
また障子(しょうじ)は、現代住宅が要求する数々の機能(採光や断熱、プライバシー保持、通気性など)を充分に満たしながら、やすらぎを与えてくれる現代的インテリアと言えます。
(4)適度な通気性
和紙ですから、呼吸をします。
冬、こたつで暖まりながらも背中がゾクッとすることがありますよね?
これは、低温の窓やコンクリートの壁にふれて冷やされた空気が床に沿って流れる「コールドドラフト(冷たい空気の流れ)」が起きているからです。
しかしこの現象は、室内の空気が直接ガラス面にふれないよう「ガラス窓+障子(しょうじ)の二重建具にすることで軽減させることができ、寒い日もより快適に過ごせます。
障子(しょうじ)では自然な形で換気と清浄化が行われるため、機密性が高まった住宅環境でここ10年間に倍増する幼児アトピーも、障子(しょうじ)を利用すれば通気性がよくなり緩和される、とのことです。
また、身体に有害なホルムアルデヒドや空気中のホコリ・ニコチンなども吸収し健康的です。
さらに、障子には吸湿性もあるため室内に湿気がこもるのを防ぎ、湿度の高い日本の住宅には最適な建具です。
(5)高い断熱効果
「えっ?」と思われるかも知れませんが、カーテンよりも2重のガラス戸よりも高い断熱性が確認されているのが障子(しょうじ)紙なのです。
最近とみに断熱効果への関心は高まりつつありますが、断熱の良い住居でも一重ガラス窓の場合、約40%の熱がガラス窓から失われています。
しかし、障子(しょうじ)を使用して「ガラス戸+障子(しょうじ)」の二重建具にすると、その熱損失は約20%、半分近くも減少することができるのです。
障子(しょうじ)には、直射日光をさえぎる機能があり、ガラスより約1/2日射熱を減少させることができます。
夏の冷房時に日射による冷房効果が低減した場合、冷房効果を保持する効果があります。
障子(しょうじ)って本当に凄いのです。